カタログ収集(制作舞台裏)
このページは、オートバイの「カタログ収集」に関する、制作舞台裏を記録したページです。
( ![]() の写真はクリックすると拡大ウィンドウが開きます)
の写真はクリックすると拡大ウィンドウが開きます)

ホンダのカタログは235部ありました。
ホンダが一番好きで頻繁に見ていたので、傷んでいるものも多いですが、それを含めて懐かしいものばかり。

ヤマハのカタログは87部ありました。
ヤマハはウェブサイトで「全ての車種」がしっかりとアーカイブ化されており、カタログの印刷識別記号も分かりやすく、作業が一番やりやすかったです。

スズキのカタログは110部ありした。
スズキのは年式を調べる作業が一番大変でした。カタログの印刷識別情報はどれも似ていて数値だけなので、ブラウザーが電話番号と誤認識する場面も。
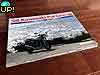
カワサキのカタログは23部ありました。
数は少ないですが、懐かしいものも多いです。
記事の目次
構想段階
実はこの企画、「いちまるホームページ」のコンテンツとして最初に考えたものでしたが、開設当時(2004年)のサーバーの容量は、わずか20MB(メガバイト)。
この企画はお蔵入りしていました。
それから15年。
ふと調べてみたら、無料で最大2,000MB(=2ギガバイト)のレンタルサーバーがあることが分かり、それまで有料の40MBのサーバーから引っ越しました。
サーバー容量を拡張して半年くらい経った頃、「カタログのアップロードも容量的にはいけるのでは?」と、お蔵入りしていたこの企画に気付いたわけです。
所有カタログの正確な部数は不明ながら、「多分収まるだろう」というどんぶり勘定で、この企画をスタートさせることを決意。
仮にサーバーの容量が足りなかったとしても、電子化による保管はやっておこう、とも思った次第です。
では次に「コンテンツの考案」。要は「どういう内容にするか」です。
これは数日あれこれ考えました。
お手本も何もない、ゼロからのスタート。「脳内一人会議」です。
でも、この「新しい形が産み出されていく段階」が結構楽しいんです。
例えば、(ホームページのコンテンツにするなら、単に電子ファイル化するだけでなく、何か追加更新するような継続的なコンテンツにしてみたいな…)などと、アイデアを巡らせる段階です。
次に実現手段の検討。
自分の決めた条件は「これ以上の費用を払わずに作成公開ができる環境が整っていること」。
スキャンとPDFファイル化に関しては、「職場の複合機とPCを借用する」という、やや反則技を駆使すれば条件をクリアすることが可能、という結論に。
ただし、職場の環境が変わらない限りは、という前提付き。
ならば急ごう(笑)
さて、どういうページ構成で整理するか。
単なるアーカイブ化では面白くないので、主観を入れて時々それをアップデートするようにしようか、などをこの段階で構想を練り上げていきました。
作業の流れ
では、作業開始。
この「いちまるホームページ」は、HTML(Hyper Text Markup Language)、つまりWebページを作成するための「コンピューター言語」をキーボードで打ち込むことで出来上がっています。
だから、埋め込むリンク、写真、表などは、すべて「その言語でタイピング入力する」という手間がかかっています。
さて、カタログの部数は「数百部」と推測。
そのスキャン作業も含めた「膨大な量の作業」を、どういう手順で進めていくか。
まずは一覧表のページを作ることにしました。
そしてその一覧表に対して、PDF化したカタログファイルのリンクを付け加えていくことにしました。
こうすれば、時間を要するであろうPDFファイルのスキャンが全て終わる前に、一覧表のページを先行で公開して、それから徐々にPDFファイルを追加更新していけるぞ、と。
では次に、どういう項目の一覧表にするか。
同じ車種や題名に対して複数のカタログが存在する場合があるので、カタログ裏表紙の隅に小さく記されている固有記号のような文字列を「印刷識別記号」と定義して、これで区別することしました。
一覧表を作成する際は、この「印刷識別記号」を一つずつタイピング入力したのですが、これがどれも小さな文字の「暗号」なので、結構な細かい作業でした。
あとは、カタログの掲載順序の基準にする最低限の項目として、「発売年(=年式)」、「排気量」、「エンジン形態」の情報を併記することにしましたが、ここで意外と難儀だったのが「発売年(=年式)」。
古いか新しいかの「順序」は整理されていたものの、それが「何年なのか」は、この機会に全て調べ直す事にしました。ところが古い車種ばかりなので、なかなか分からないものも多数。
予想以上に時間を要しました。
排気量に関しては、正確な数値を載せることにしたので、これも手間といえば手間でした。(例えば750ccのバイクでも、実際には748ccとか747ccとかという具合に違う場合もあるので)
スキャン(デジタル化)
手入力のHTMLによる表の作成を先行させながら、カタログのスキャン作業も並行して始めたわけですが、職場の複合機をスキャナーとして「無断借用」するので、始業前や昼休みなどの勤務時間外に「こっそり」&「細切れで」やるしかありません。
このスキャン作業。
…予想をはるかに上回る「集中力を要する作業」でした。
目立たないように、こっそりとハラハラしながら焦って作業するから、という理由もありますが、カタログのレイアウトによってスキャンの仕方が都度変わるから、という理由があります。
代表的なレイアウトとスキャンの仕方は次の通りです。
変形?A4判
A4判の寸法は[297×210mm]ですが、古いカタログは、短辺側が約10mm短い[297×199mm]というものが多数ありました。
これを仮に「変形A4判」と称するとしましょう。
でも、スキャナーの読み取りサイズにそんな中途半端な設定はないので、設定は「正規のA4サイズ」でスキャンをします。
カタログが正規のA4判の場合は、カタログを置く場所はスキャナーの左と奥の「隅っこ」に合わせるので、簡単だし曲がったりする心配も不要なのですが、この変形A4判をセットする時は、同じように隅に合わせて置いてしまうと片側の余白が多くなって偏ってしまうので、目分量で長辺側(=横長上下)の余白が均等になるようにセットするという配慮が、「全ての」ページをスキャンする際に必要となります。
やっかいなのは、この「変形のA4判」は正規のA4判に数多く入り混じっていること。
そして、後述する「用紙の向き」とか「原稿サイズとか」の他の事に気を取られていると、集中力が持たずに用紙を置く位置の区別を忘れられがちになること。
忘れて偏ったままPDF化されたカタログも多数あると思いますが、これは諦めました。
ちなみに海外用のカタログは、さらに異なる「変形A4判」もありましたが、これらは部数とページ数が少ないので、普通にA4判としてスキャンしました。
A4・短辺・見開き
このレイアウトが一番多かったように思います。
まず、スキャナーにカタログ原紙を置く位置を、左と奥の「隅っこ」にしたいので、奇数ページと偶数ページでは、それぞれ上下逆さまの状態でスキャンすることになります。
最初の頃にスキャン作業をしたホンダのカタログは、向きを変えずにスキャンしていましたが、ページの隅が浮いてしまい、やや変形して映り込んでしまうので、途中からは上下逆さまの手間を加えて、すべて左と奥の「隅っこ」に置くことにしました。
この事は、スキャン作業においては大した手間ではないですが、スキャンしたデータを編集する際に、反転しているページを元に戻す、という手作業を招きます。
さらに、見開きにした2ページが1つのレイアウトになっているカタログが多数あります。
これを普通にA4サイズでスキャンすると、ブラウザーでそのPDFファイルを開いた場合、2ページにまたがった写真や文章は分断された状態で見にくくなってしまいます。
しかし、A4の横長方向の2ページはスキャナーでは一括では読み取れません。
そこで苦肉の策として、そのような見開き2ページの場合は、左・中央・右の3枚をスキャンすることにしました。
このようにしたPDFカタログは、写真などが分断されずに見やすくなりましたが、このやり方は途中から採用したので、初期の頃にスキャンしたホンダのカタログは、全数チェックして該当するカタログを改めて探すという手間が加わりました。
ちなみにA4またはA3の見開き追加スキャンは、ホンダで約100部!
「追加」とは言え、この100部はかなりの量。しかもPDF化の作業は実質やり直し。
さて、話を戻して「2ページの真ん中を追加スキャンする件」ですが、これをやった場合は、カタログ1部のあたりの総ページ数が奇数になることもあります。
このスキャン方法を実践する前は、最終ページをスキャンすると時にそれが何枚目かを見て、それが奇数ならスキャンを忘れたページがある、と簡易的に判断できていたのですが、それができなくなったので、さらに集中力が要求される作業になりました。
A4・長辺・見開き
このレイアウトは少なかったように思いますが、分かりやすさで言えば、比較的楽なパターン。
見開き状態ではA3判になるので、借用したスキャナーで読み取れる範囲だからです。
ただし、少なくとも表紙と裏表紙はA4判だし、解像度の事を考慮してA3判でスキャンする見開き2ページの部分も、念のために各ページをA4サイズでもスキャンすることにしました。
つまり、1部のカタログのスキャンの途中で、スキャナーの読み取りサイズの設定を変える必要があるのですが、読み取りサイズの変更にはボタンを最低でも3回押すので、これが結構面倒に感じるのです。
ここでさらに悩ましいのが、この変更作業を最小限にしようと、1部のカタログからA3サイズの部分だけをまとめてスキャンしたくなる衝動に駆られるのですが、これをやるとスキャンするページの順番を脳内で記憶する必要が生じて、長時間のスキャン作業や、限られた時間で焦って作業すると、どうしてもミスが生じやすくなりまる、ということです。
そして、仮に集中力が持ったとしても、結局は編集する際にページの位置を入れ替えるための集中力が必要となるので、どっちにしても手間なのです。
このカタログレイアウトは、スズキの初期型のGSX-R750やRG400γなど、気合の入ったモデルで採用されていて、冊子として鑑賞するには写真も大きく、良いレイアウトなのですが、スキャンの手間とページ数は多くなります。
ヤマハのTT250Rに至っては、実は表紙と裏表紙も開くとA3判になるレイアウトだったりして、スキャン作業中は油断はできないのです。
A4・短辺/長辺見開き・6ページ
総ページ数が「4の倍数」のレイアウトの場合は、A3の紙が半分に折られた造りで、8ページ以上の場合は「つづり針」(=ホッチキスの針)で製本されますが、これらのレイアウトに2ページを追加した「6ページ」などのレイアウトになると、一辺が「袋とじ」のような状態で折られたページが混在します。
一番多いのが、A4判横向きの表紙を左開きで開いた時に、開いたその両2ページの右側のページが短辺袋とじになっているレイアウト。
袋とじのページを右側に開くと「A4判を横長に3枚並べた状態」で開かれた形になります。
このレイアウトのカタログのスキャンは、また別の集中力と手間を必要とします。
何故かというと、構成パターンが2種類あるからです。
ひとつは、「袋とじ」の見開きページが閉じた状態において、ページ構成の順番として、左側のページが2ページ目、右側のページが3ページ目になる構成。
もう一つは、逆に右のページが2ページ目で、左のページが3ページ、そして「袋とじ」を展開すると左側のその3ページとつながる形で4〜6ページとなる構成です。
つまり、どちらのページ構成かを判断すために、注意力が取られます。
さらに前述の「A4・見開き」での「上下の向きの入れ替え」、長辺見開きの場合は「読み取りサイズの変更」の作業も加わります。
とても集中した作業が必要となりました。全部がこのレイアウトという事ではないので。
A4・四つ折り
これは、ページ数は4の倍数ですが、A2判が四つ折りになったレイアウト。
大きなポスターのようになります。
スズキの総合カタログの多くがこのパターンです。
壁に貼る場合は重宝しますが、スキャン作業泣かせとも言えます。
前述の各種レイアウトで必要となる集中力の全てが必要となり、さらに紙を手で押さえるという追加の作業が必要となる場合もあります。
表紙と裏表紙はいいです。スキャナーの読み取りサイズを「A4・横」にして、用紙を左奥の隅っこにおいてスキャンします。
次です。その「A4・横」の読み取り設定のまま、見開きにしたA2判ページ(=A4判×4枚)の「右上」と「左下」のA4判範囲をスキャンします。
左奥に合わせて置く都合上、上下の向きはあべこべになります。
残りの「左上」と「右下」は、用紙を左奥に合わせてスキャンするために、スキャナーの読み取りサイズの設定を「A4・横」から「A4・縦」に変更して、読ませます。
そして今度は、スキャナーの読み取りサイズを「A3(横のみ)」に再び変更して、その状態で左・右の半分ずつをスキャン。この時に、これら左右にまたがったレイアウトの場合は、中央も1枚追加でスキャンします。
この時は用紙を押さえるための複合機のカバーが閉められないので、手で押さえます。
この時に、変形A4判だとさらに大変。
なぜかというと、スキャナーの読み取りサイズはあくまでA3判なので、余白ができます。しかし用紙を押さえるカバーを閉められないので、そこに白い紙などを置く必要があります。
それらを、左右の余白を均等になるように手で調整しつつ、ずれないように押さえ込む。
無事にスキャンが終わった後のデータは、ページの順番がオリジナルとは違うし、向きも右・左・上下のすべての補正が必要となります。
…なんとも手間のかかるスキャンです。
…なんて長い説明なんだ!(疲)
かくのごとく、スキャン作業はややこしさがあり、平日の勤務時間外では、1日でカタログ3〜5部くらいしか進みません。
そこで、休日に職場に行って、一気にスキャン作業をした事も5回ほどありましたが、前述のような「様々なパターン」に対して、ミスなくスキャン作業を行うための集中力と精神力を長時間に渡ってキープする必要があり、その時の疲労度といったら、結構なものでした。
編集
こうして手間をかけてスキャンしてデジタル化されたデータは、ファイル形式こそPDFですが、ファイル名は長い数値の羅列です。
このファイル名のままでは、ファイルを開かないと何のカタログか分からないので、これらに新たにファイル名を手入力で付けていきます。
中には、同じ車種で複数のカタログがあるので、ファイル名の区別とそのルールを自分で考えておく必要もありました。
つぎにファイル名を付けたPDFファイルですが、スキャン作業の都合上、ページの向きはバラバラで、さらにページの順番が違うものもあります。
これらを一つずつ手作業で、PC画面上で直してから上書き保存します。
ここまでの作業も結構な手間がかかりますが、「いちまるホームページ」で使うためにさらに作業が必要となります。
それは、「ファイル容量を小さく変換する作業」です。
スキャンしたままのPDFファイルの容量は合計で2,120MB。これはこれで自分用に保管するとして、このままではいちまるホームページ用のサーバーには収まりません。
そこで、解像度は多少落ちますが、ファイル容量を縮小させる変換作業が必要となります。
この変換により、合計のファイルサイズは365MBにまで縮小させました。
これらの変換したファイルには、別のファイル名をつけてホームページ用に保存します。
この変換作業は、家のPCのソフトウエアではできず、会社が支給したノートPCで行う必要がありました。
そして、変換作業は1ファイルあたり30秒くらいで終わるのですが、まだ終わりではないのです(喘)。
なぜなら、この変換作業により、ページの縦・横の向きが全て揃ってしまうからなのです。
縦と横のページが混在するカタログも結構あるので、ここで改めて個々にチェックした上で、ページの向きを変更させる手作業が必要となります。
これでようやく!いちまるホームページ用のPDFファイルが完成です。
残るのは、HTMLの一覧表にそれぞれのカタログに対する「リンクを張る」という作業です。
コピー&ペースト作業が中心なので、それまでのスキャン作業やその編集作業と比べると、「単調」ではあるものの、HTMLの文字列の中に埋め込んでいくので、「眼力」と「集中力」が求められる細かい作業です。
また、アップロードするPDFファイルの最終確認もここで行うので、一つずつアップロードしてはファイルを開き、次にまた…という確認しながらの作業なので、やはり時間もかかりました。
実際、やり直しが必要なファイルもそこそこ見つかり、やり直し作業はその場(自宅)ではできないので、カタログの原紙から必要な分だけを抜き、会社でスキャンを変換をやり直したあと元の位置に戻す、という作業も割と手間がかかりました。
最後にいよいよ、編集したHTMLデータとPDFファイルをサーバーにアップロードして、更新の記録を書き添えて…、ようやく完成!!
その後は、無作為にピックアップしたカタログとそのコメントについて、懐かしみながら少しずつ追加更新していこういと思います。
当初は、そのオートバイに対する自分の「思い出」や「感想」のようなものを書こうと思っていましたが、カタログの整理を重ねていくにつれて、カタログという「作品」に対するコメントの方が楽しそうだと思うようになってきました。
とにかく!どれも「作品」として素晴らしいと思います。
しかもその題材が、自分にとって懐かしいオートバイたち。
この企画は、根気を要する作業でしたが、よく頑張った!自分。
写真の「加工・編集」
この企画の構想段階から思い描いていた、「追加更新する継続的なコンテンツも」というアイデアは、無作為にピックアップしたカタログについて「写真とコメント」をつけて追加更新していく、というものです。
そこで使う写真は、単にカタログの表紙をピックアップするのは面白くないと思い、カタログの中から「良さそう写真」を選ぶようにしています。
そうすると例えば、「この写真を使いたいけれど、文字などが邪魔」とか、「所定の枠内にいい感じで収まらない」という事で、写真を「加工・編集」したくなる欲求が沸いてきました。
最初の頃は「余分な線を消去する」とか、その程度の簡単な「加工・編集」でしたが、この「加工・編集」自体が楽しくなってきて、実は結構な手間をかけた写真も多数あります。
一例をあげるとこんな感じ。(左の写真が加工前、右の写真が加工後)
 →
→

この例では、次のような処理を施しています。
「加工・編集」の作業は、手間暇をかけるほど完成度も上がり達成感も得られますが、一方で完成度が上がるほど「その苦労に誰も気付かない」というジレンマがあるのは少々悩ましいところではあります(笑)。